土壌環境保全
豊かで美しい未来へ
Daigasグループでの実績を活かした最適な土壌汚染対策をご提供いたします。事業者・土地所有者様の視点にたって、調査から対策工事、リスクコミュニケーションまでをトータルにサポートします。
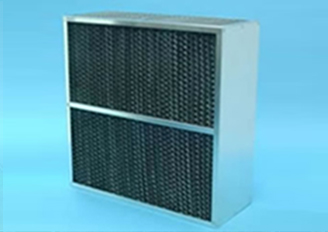
実践力
豊かで美しい土地を未来へ
Daigasグループでの実績を活かした最適な土壌汚染対策をご提供いたします
大阪ガス社有地で得たさまざまなノウハウを糧に、高度で多様化する土地活用のニーズにお応えします。
Daigasグループでは、国内のエネルギー事業者の中でもいち早く土壌汚染の存在を公表し、汚染実態の把握に努めてまいりました。さらにリスク低減対策や地元の方々へのご説明をはじめとする 誠実な取り組みは、地元の方々や行政から高い評価と信頼を得ています。私たちDaigasガスアンドパワーソリューションは、当初から大阪ガスと一体となって土壌環境をめぐる課題に真摯に向き合い、さまざまな技術を開発 してきました。これまで蓄積してきたノウハウを質の高いサービスに変えてご提供することで、高度で多様化する土地活用のニーズにお応えしていきます。
事業者・土地所有者様の視点にたって、調査から対策工事、リスクコミュニケーションまでをトータルサポートします
土壌・地下水汚染は、不動産という財産の評価・価値に大きく関わる問題であると同時に、事業者・土地所有者様にとって重要な課題のひとつです。Daigasガスアンドパワーソリューションでは、大阪ガスでの土地所有者側に立った コンサルティングの経験を活かし、事業者・土地所有者の視点で調査から対策工事、リスクコミュニケーションまでをトータルにサポートしています。各ステップの連携がスムーズになり、コスト削減に つながるワンストップサービスにより、お客さまの満足度を高め、より高品質なサービスをご提供いたします。
法律と基準
土壌汚染対策法の概要
法の目的
土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
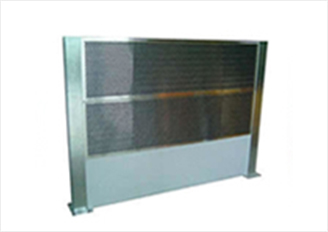
法の対象となる物質と汚染状態に関する土壌の基準及び地下水基準

解決力
汚染の調査・分析から浄化までの流れ
「確かな提案力」「最先端の技術力」「万全の機動力」を駆使して、 調査からリスクコミュニケーション、対策工事、モニタリングまでの ワンストップサービスを実現。

0.土壌調査の必要性(調査の契機)
土壌汚染対策法では、①有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された場合、②一定規模以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると 都道府県知事が認める場合、③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合に、土壌調査を行うことを義務付けています。また、 法や条例に基づかない土地売買等に伴う自主調査も多く行われています。
調査の契機
・土壌汚染対策法に基づく調査
・条例・要綱に基づく調査
・自主調査(土地売買、小規模な土地改変、土地資産評価、ISO等)
1.地歴調査
調査対象地及びその周辺の土地について、現在及び過去における利用履歴、特定有害物質の使用状況、その他有効な情報を入手・把握し、調査対象物質の特定及び調査対象地における土壌汚染のおそれを分類します。
調査対象物質の絞り込み
法の対象となる物質(特定有機物質)として、土壌に含まれることに起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして25物質を指定
調査対象地における土壌汚染のおそれを3つの区分に分類
・土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地
・土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地
・土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地
2.現地調査(汚染の有無を平面的に把握する)

日地歴調査の結果に基づき現地にて資料採取等を行い、汚染の有無を平面的に把握します。
土壌ガス調査
~調査対象物質が第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の場合~
地表面下0.8~1.0mの深度の土壌ガスを採取し、検出された場合は、深さ10mまでの土壌溶出量調査を行い、汚染状態を評価する。
表層土壌調査
~調査対象物質が第二種(重金属等)、第三種(農薬等)特定物質の場合~
地表面下0~0.05m、0.05~0.5mの深度の土壌を採取、均等混合した試料を分析し、土壌汚染の有無を確認します。(溶出量と含有量が基準に適合しているか確認)
3.詳細調査(汚染の範囲を立体的に把握する)

表層調査の結果、基準不適合が確認された区画については、深度方向の汚染範囲を特定します。
a.調査対象物質
表層土壌調査の結果により、土壌汚染が確認された物質について実施。
b.調査対象区画
表層土壌調査の結果により、土壌汚染が確認された区画について実施。
c.調査対象深度
表層下10mまでボーリングを実施する。試料は1m、2m、…以下1mごとに採取し、分析を実施。
d.調査方法
| 調査対象物質 | 調査内容 |
| 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) | 土壌溶出量調査 |
| 第二種特定有害物質(重金属等) | 土壌溶出量調査 / 土壌含有量調査 |
| 第三種特定有害物質(農薬等) | 土壌溶出量調査 |
4.リスクコミュニケーション

事業者と周辺住民、自治体が双方向のコミュニケーションをとりながら、相互に情報を共有して理解し合い、信頼関係を構築して円滑に土壌汚染対策を進めるために行うプロセスです。
5.対策内容立案・実施
対策内容立案・実施の詳細は「対策の具体例」を参照
6.地下水モニタリング
対策完了後、効果が持続しているかどうか、観測井戸を用いて地下水モニタリングにて確認します。
| 対策の種類 | 水質の測定頻度 | 確認事項 |
| 地下水の水質の測定 | 1)措置の完了報告を行わない場合 1年目定期的に4回/年以上 2〜10年目1回/年以上 11年目以降1回/2年以上 |
地下水汚染が生じるおそれがある場合には以下の措置に移行する |
| 2)措置の完了報告を行う場合 上記1)の測定を5年以上継続して実施し、かつ直近の2年間は4回/年以上 |
目標地下水濃度を超える恐れがあるう場合には以下の措置に移行する | |
| 原位置封じ込め | 4回/年以上 | 目標地下水濃度を超えない状態が2年間継続すること |
| 遮水工封じ込め | ||
| 土壌汚染の除去(原位置浄化) | ||
| 遮断工封じ込め | ||
| 不溶化 (不溶化埋め戻し) | ||
| 地下水汚染の拡大の防止 (揚水施設) |
4回/年以上 | 地下水汚染が拡大していないことを確認すること |
| 地下水汚染の拡大の防止 (透過性地下水浄化壁) |
4回/年以上 | 目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水が拡大していない事を確認すること |
| 土壌汚染の除去 (掘削除去) | 4回/年以上 | 目標地下水濃度を超えない状態が2年間継続すること(ただし、措置実施前に目標地下水濃度を超えていない場合、1回) |
対策の具体例
溶出量基準に適合しない土壌に対して、地下水の摂取等によるリスクに係る措置

地下水の水質の測定

原位置封じ込め

遮水工封じ込め

地下水汚染の拡大の防止
(揚水施設、透過性地下水浄化壁)

土壌汚染の除去
(掘削除去、原位置浄化など)

遮断工封じ込め

不溶化
(原位置不溶化、不溶化埋め戻し)

PRB施工図
含有量基準に適合しない土壌に対して、直接摂取によるリスクに係る措置

舗装

立入禁止

土壌入換え(区域内土壌入換え)
(区域外土壌入換、区域内土壌入換)

盛土

土壌汚染の除去(掘削除去)
(掘削除去、原位置浄化など)
指定調査機関
A.指定調査機関情報
| 名称 | Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 |
| 指定番号 | 2020-8-1001 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 |
| 電話番号 | 06-6205-2961 |
| 事業所の所在地 | 大阪府大阪市 |
| 業の登録・許可の状況 | 建設コンサルタント業/建設業/1級建築士事務所 |
| 技術管理者数 | 5人 |
| 土壌汚染調査の従事技術者数 | 9人 |
| ホームページアドレス | https://www.daigasgps.co.jp/service/engineering/environment/countermeasure/ |
B.技術力(技術者の保有資格と資格保有者数)
| 土壌汚染調査技術管理者 | 5人 |
| 土壌環境リスク管理者 | 4人 |
| 土壌環境保全士 | 2人 |
| 1級土木施工管理技士 | 7人 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1人 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 2人 |
| 公害防止管理者(大気1種) | 1人 |
| 技術士(補) | 3人 |
C.業務品質管理の取組(業務品質管理の取組状況)
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質の管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施。
